マイクロ法人やってみる?
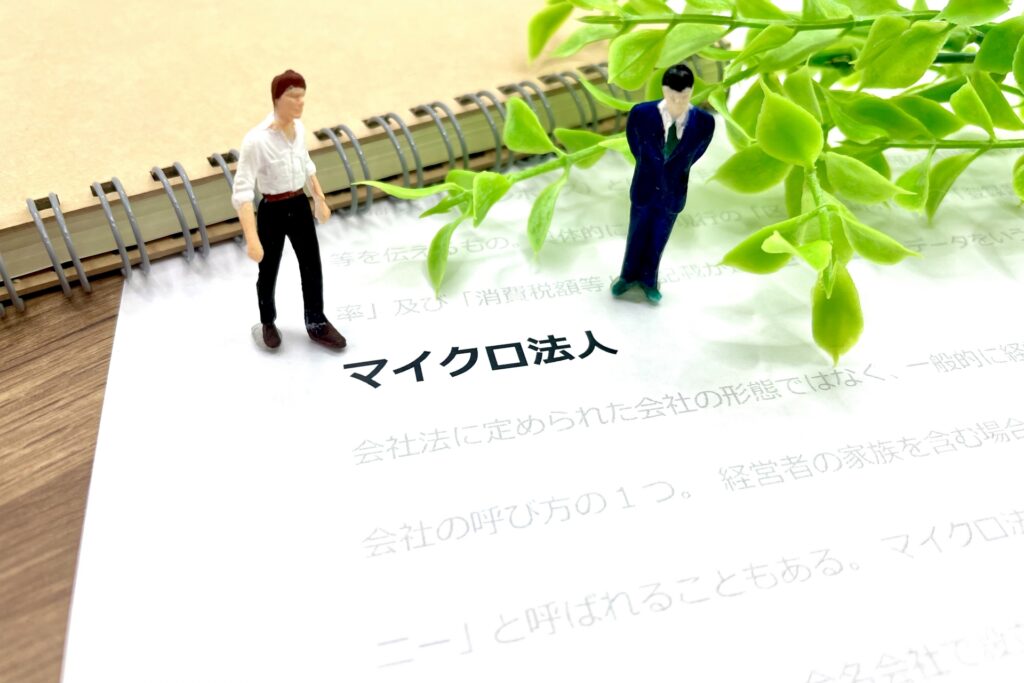
マイクロ法人?
最近よく聞くけど、マイクロ法人って何?についてご説明します。
会社法の中に「マイクロ法人」というくくりがあるという訳ではないのです。
個人事業主が小規模(マイクロ)な会社を設立して、個人事業主の立場と、法人の役員の立場を併存させることで、年金、税、健康保険料などの負担を軽減するための一つの方法をもって、「マイクロ法人」と言われているのがここ最近です。
特に、稼ぎのいい個人事業主の場合、国民健康保険料がだいぶお高いので、なんとかなったらいいな、というときの一つの方法として、マイクロ法人を持つ、というのがあります。
事業の一部を法人化する
事業の一部を法人化する、というマイクロ法人のスキームでは、個人でおこなっている事業の一部を、新しく設立する会社の事業とすることによって、そのマイクロ会社の事業に関してマイクロ会社から役員報酬を受け取るようにします。
一般的な会社と違うのは、事業拡大を目指すかどうかという点です。一般的な会社は、利益の維持や向上のために事業拡大を目指し、得た利益は株主などに配分します。
一方、マイクロ法人は、出資者である株主と経営者の役割を同一人物が両方兼ね、1人でできる範囲で事業を行います。1人でできて、かつ設備費や仕入れ費用が抑えられるような業種に向いていると言えます。
大きなメリットが2つ
マイクロ法人を設立すると、個人事業主として事業を続ける場合に比べ、さまざまなメリットがあります。ここでは特に大きなメリットの2つをご紹介します。
1.節税効果が高い
マイクロ法人の場合、個人事業主よりも、経費にできる範囲が広く認められています。経費とは、事業を行うために必要な費用のことで、経費として認められたものは、所得から差し引くことが可能です。所得が減れば、税金も減るので、節税効果があります。
たとえば、法人の経営者は役員報酬を受け取りますが、要件を満たせば役員報酬は経費として扱うことが可能です。役員報酬を経費として扱えれば、法人の所得が減るため、節税効果を高めることにつながります。
法人であれば経営者の退職金も損金計上できるだけでなく、生命保険の一部や出張の際の日当も経費として扱うことも可能です。
また、個人事業主は累進課税制度が採用されているため、複数事業を運営して所得が増えると税率が高くなります。しかし、マイクロ法人を設立すると、個人事業とマイクロ法人に所得を分散でき、全体の所得を減らせるため、節税につながります。
そして、役員報酬は給与所得のため、給与所得控除が受けられます。給与所得控除とは、給与所得から一定の金額を差し引かれる控除です。給与所得控除の金額は、給与収入の額に応じて変わります。
さらに、マイクロ法人として社会保険に加入すれば、役員報酬の金額を可能な限り下げることによって、健康保険と厚生年金の保険料を抑えることが可能です。個人事業主の場合は、国民健康保険や国民年金に加入する必要がありますが、これらの保険料は所得に応じて増えます。マイクロ法人の場合は、役員報酬を調整することで、保険料の負担を減らせるでしょう。
2.社会的な信用度が高くなる
法人を設立する際には、法務局に法人登記(会社設立登記)を行います。法人登記の目的は、商号(社名)や住所、資本金などの情報を開示して会社の信頼維持を図り、安心して取引ができるようにすることです。
登記した内容は誰でも閲覧できるため、法人としての責任が発生し、社会的な信用度が高くなります。たとえば、大手企業は個人事業主と契約を結ばなかったり、取引金額を抑えたりする場合もありますが、マイクロ法人なら取引できることもあるのがメリットといえでしょう。
また、社会的な信用度が向上すると、金融機関からの融資を受けやすくなる可能性があります。個人事業主でも資金調達は行えますが、マイクロ法人なら、法人を対象にした補助金・助成金制度も利用できるようになります。
デメリットはないの?
節税や社会的信用度の向上などのメリットがあるマイクロ法人ですが、デメリットもあります。ここでは、マイクロ法人を設立するデメリットについて、詳しくみていきます。
〇会社の設立・維持に費用と手間がかかる
マイクロ法人を設立するには、個人事業主と比べて、より多くの費用と手間がかかります。
まず、会社の設立には、定款の作成や認証、法人登記などの手続きが必要です。これらの手続きには、登録免許税や収入印紙代などの費用が発生します。また、自宅以外に事務所を借りる場合などにもその分の費用がかかります。
〇決算書や税務申告書などの書類の作成が必要
これらの作業には時間がかかり、作業中は営業活動ができません。決算書や税務申告書は自分でも作成できますが、個人の確定申告に比べて複雑になっています。
〇赤字でも法人住民税を支払わなければいけない
法人を設立すると、赤字でも法人住民税を支払わなければいけない場合があります。
法人住民税は、都道府県民税と市町村民税の2種類からなりますが、都道府県民税と市町村民税には、法人の所在地に基づいて課される均等割という税金があります。均等割は、法人の所在地の都道府県や市町村が定めた一定の金額を、資本金や人数に応じて分担して納める税金です。
均等割の金額は、市町村によって異なりますが、一般的には数万円から数十万円程度です。均等割は、法人の所得に関係なく課される税金なので、赤字でも支払わなければいけません。
このため、マイクロ法人を設立する場合は、赤字になったときにも均等割を支払えるだけの資金を確保しておく必要があります。
〇決算申告などの税務処理コストがかかる
マイクロ法人を設立すると、個人事業主とは異なり、決算申告などの税務処理コストがかかります。決算申告は、法人の所得を計算して法人税を納めるための手続きです。
正確な税務処理のためには自分一人だけで行うより、税理士さんに依頼する方が効率が良い場合もあるため、マイクロ法人を設立する場合は、これらの税務処理コストを見込んでおくことが大切です。
株式会社か、合同会社か
マイクロ法人を設立するぞ、と決めたとして、株式会社と合同会社、どちらにしようか、と考えた場合、設立費用が安く済む合同会社を検討される場合が多いと思います。
合同会社の設立は、株式会社の設立に比べ、実費部分だけでもだいぶ安く済みます。
主な実費である設立の登録免許税は、株式会社だと一番少なくても15万円。合同会社だと6万円です。さらに、定款認証が必要な株式会社は公証人の定款認証手数料で平均5万円ほどかかります。一方、合同会社は設立登記において定款認証の必要がありません。
ただ、その後の会社の運営を考えると、株式会社と合同会社はだいぶ違いがあるので、運営に都合の良い方はどちらかを見極めるひつようがあるでしょう。
当事務所では、会社設立の流れや費用についてコラムでご紹介しています。→こちらからどうぞ
どんなこともお気軽にご相談くださいね。
